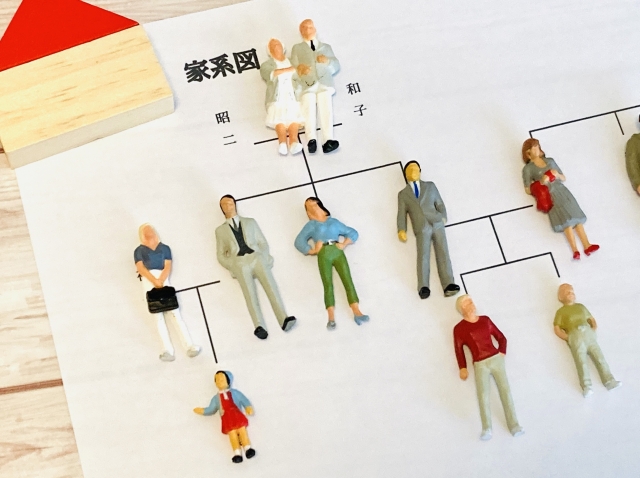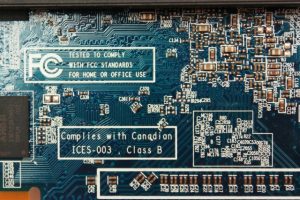相続税はここ10年で基礎控除をはじめとして、さまざまな制度設計が変更されてきました。前提として「より多くの方が課税対象になる」方向での変更です。従来の制度では相続税の課税対象となっていた人が、対象から外れることは一部の新設の特例適用などを除きありません。
それだけ国は税収源として、相続税(および贈与税)に期待していることがわかりますが、取られる方は溜まったものではありません。今回はそんなご時世の中、【個人で相続税対策を考えないといけない人には、どのような特徴があるのか】について、注意点と合わせてお伝えします。
なぜ相続対策が必要なのか
相続に向けた対策についての考え方は大きく分けて二つ「相続対策」と「相続税対策」があります。これらは厳密に異なるもので、それぞれが必要な理由は異なります。
まず前者の相続対策は、相続に向けた資産のポートフォリオ(組み合わせ)の適正化が目的です。家族それぞれが納得できる形に相続資産を整備し、将来の相続に備えます。またここには口座情報の管理や資産の見える化などの、いわゆる「終活」活動も含まれます。
後者の相続税対策は、前項を踏まえ「相続税がいくらになるのか」「それを支払うことができるのか」「どうすれば減らすことができるのか」といった内容になります。
相続税の考え方
次に相続税に関する考え方です。相続税は、すべての相続案件に適用される基礎控除と、相続資産を承継する権利のある法定相続人(被相続人の配偶者や子ども、兄弟など)に課税額を減らす控除が付与されています。基礎控除は3,000万円、法定相続人は1人あたり600万円の控除額です。
<法定相続人が妻、子ども2人の場合>
| 基礎控除3000万円+(3人×600万円)=4800万円 |
この家族構成の場合、資産の合計が4800万円以下であれば相続税はかかりません。この計算式によって算出した相続税額を、基本的には資産を承継する相続人間で定められた法定相続分で按分します。これは民法で定められています。
<民法による資産配分>
| ① | 相続人が「配偶者・子」 | 配偶者1/2、子1/2 |
| ② | 相続人が「配偶者・直系尊属(両親)」 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
| ③ | 相続人が「配偶者・兄弟姉妹」 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
この「4800万円」という数字を出すと、相続は富裕層の問題だから自分たちには関係無いという話をよく耳にします。これはとても危険な考えです。金額の対象となる相続資産には、持ち家や会社の株も対象となります。また東京や大阪などの政令指定都市では、家があるだけで相続税が発生する可能性が高いです。また会社の場合、1000万円以上の利益(役員報酬を含みます)があれば課税対象になる可能性が高いです。
相続税を節税すること
よって資産を承継する家族にとって、相続税の支払いはとても大きな負担となります。そこで元気なうちに「自分が亡くなった場合、相続税はいくらかかるのか」を計算することが大切です。支払う金額が少しでも減らせるように、特例や非課税枠などを活用する対策が相続税の節税です。
後ほど詳しく書きますが、近年の税法改正で「こういった相続税対策は、相続発生(死亡)から7年、アクションをさかのぼって無効」とされる法律ができました。つまり急に準備しても間に合わなくなったということですね。
また安易に、遺言書を残しておけば安心!と考える方もいらっしゃいますがそれも違います。後述しますが、遺言状を残しても揉めるケースがあります。
蛇足ながら節税は法律などに抵触せず進めるため、決して違法性のあるものではないため安心しましょう。とはいえ、なかには近年有名になったタワーマンション節税のように、従来は問題無かったものの、国税庁や税務署の見解変化で状況が変わっているものもあります。ですのでネットの検索レベルの知識や怪しい広告・営業に載せられるのではなく、FPや税理士、弁護士などしかるべき専門家に相談することが大切です。
相続税対策の種類
具体的な相続税対策にはどのようなものがあるかを見ていきましょう。
不動産を活用する
代表的なものが不動産の活用です。不動産は現金と比べて、割安の評価額(相続時に適用される価格)が設定されています。この金額の差を活用することによって、節税することができます。また投資用不動産はキャッシュを生むため、相続資産を増やすことも可能です。
生命保険を活用する
もうひとつの方法が生命保険への加入です。生命保険には「法定相続分×500万円」」の非課税枠があります。万が一の場合に発生する生命保険金にプラスして、非課税枠を活用することができます。
生前贈与を活用する
相続を待たずとも、相続税を節税できる方法が生前贈与です。生前贈与に対しては相続税と同様に贈与税が課税されますが、年間110万円までは基礎控除を活用することができます。また次世代が教育資金や結婚・子育て資金を活用する場合は、更に大きな金額を非課税の対象とすることができます。また贈与時には課税せず、さまざまな特例がある相続時に合わせて税金を支払う仕組みもあります(相続時精算課税制度)。
これらが一般的な相続税対策となりますが、それ以外にも「法人を設立する」「孫を養子縁組する」「持ち家を賃貸に出す」などなど、いろんな方法があります。あくまで参考事例としてご参照ください。
相続対策が必要な人はどんな人?
では相続対策が必要な人には、どのような特徴があるでしょうか。
自分の「相続税評価」を知らない人
現金や上場株式等であれば具体的に「いくらの価値がある」ということが分かりますので、本記事で紹介した公式をあてはめていただければ大丈夫です。
ですが、例えば「持ち家」がある、「会社を経営している」、ちょっと特殊なケースだと「賃貸経営を行っている」などのケースの場合、そもそも「相続税がかかる可能性があるのか」からチェックする必要があります。
現有資産の移転が進んでいない人
資産を多く所有していることは、相続時に高い相続税が課税されることに繋がります。相続税の額が分からなくとも、「しかるべきやり方で次世代に贈与」していくことが大切です。これが進んでいない人は要注意です。
まだまあ相続は先の話なので相続準備はいずれ、という人も、先に紹介した「7年ルール」も加味すると意外と先のことではなくいつ相続が発生するかわかりません。このように現有資産(現時点で所有する資産)が次世代への移転が進んでいない人も、相続対策の必要性が高いといえるでしょう。
現金と上場株式等、有価証券の資産が中心
現在の資産が不動産や生命保険ではなく、現金中心の人も相続対策が必要です。さまざまな特例が活用できる資産ではなく、かつ相続税評価額の高い現金・上場株式等の有価証券での資産が多い人は、早急に相続対策を進める必要があります。
ここで気をつけたいのは、可能な限り現金を少なくして、不動産や生命保険に加入するといった意味ではありません。相続税を支払うため、一定程度の現金も必要です。必要以上の現金を有していることで、節税対策次第によっては余分な相続税を支払うことになってしまうことを避ける目的があります。何よりも、営業に載せられて変な保険や不動産を購入した結果、支払いが減る相続税以上に損をしてしまえば何の意味もありません。
くれぐれも、ご注意ください。
公的遺言を作成していない
相続の最大の難点は、実際に相続が発生するときに資産の出しては意見を伝えられないことです。草葉の陰から見守る代わりに、公的遺言の作成が推奨されます。公的遺言は弁護士立ち合いで自筆のものや、公証役場に出向いて公証人のもとで作成するものがあります。それぞれ特徴に違いはありますが、総じて作成することで、相続におけるリスクを軽減することができます。
ちなみにですが、公的なものではなくとりあえず「遺言を書いておけば大丈夫だろう!」というのは間違いです。なぜかと言いますと、第三者がちゃんと証明できるものでなければ不満を持った親族が「この遺言状が作成されたときはボケてて意思決定能力がなかった!!無効だ!!」という形で争いになるからですね。
くれぐれもご注意ください。
早急に専門家に相談することの意味
記事を通して、どのくらい相続対策を考えなくてはならないかを考えるきっかけになったと思います。専門家といえども、まずはライトな状態からの相談を受けていますので、一度気軽に相談してみるようにしましょう。
自分たちでは「まだ相続準備は先の話」と構えていても、実は早急に手を打たなくてはならない事柄があったり、万が一の事態に備えておかなくてはいけなかったりという事例が数多くあります。
税務署の調査が厳しくなっている?
2024年4月24日のNHK関西向けニュースで、興味深い記事が配信されました。大阪市内で不動産賃貸業を営んでいた資産家の相続で、大阪国税局は妻や子どもに9億円あまりの申告漏れを指摘していたというニュースです。興味深いのは記事内に記載された国税担当者のコメントです。「相続税は『身近な税』になっているので、財産を相続した際には申告が必要かどうか確認して、忘れずに納税して欲しい」というものでした。
国税のスタンスとしては、相続税は富裕層を対象とした特別な税金ではなく、誰しもが支払う対象となる可能性がある税金という位置づけです。今後も、このような摘発の事例は増えていくことでしょう。
家族同士が揉めないように「争族」対策を
自分の身に何かがあったときに相続について考えるのは、長らくタブー視されてきました。ただ近年は従来の価値観を上回るように、早くから相続のことを考える傾向が広がっているように感じます。その背景は、準備が不十分なまま相続を迎え、「争族」になることが、残された家族にとって大きな問題と損失になるためです。さまざまなトラブルが報じられて、少しずつ機運が高まってきたことがわかります。
相続の準備において何よりも重要なのは、専門家に早めに相談することです。早期相談をすることで、相続直前では難しい選択肢を含めて「どう動くべきか」を検討することができます。
最後に、少し宣伝です。当メディアを運営する「金融商品を売らない投資と財務の専門家」BFPホールディングスおよび、【BFPのフランチャイズ】会員に加入されている、当記事執筆者である株式会社FP-MYSの工藤 崇は、相続に対しても無料ヒアリング面談をオンライン受け付けています。
今回の記事をきっかけに、気になることが出た・できた方は、雑談ベースで構いません。「こんなこと、相談してもいいのだろうか?」と考える前に、ぜひお気軽にご利用ください。
お申し込みは以下のバナーから。